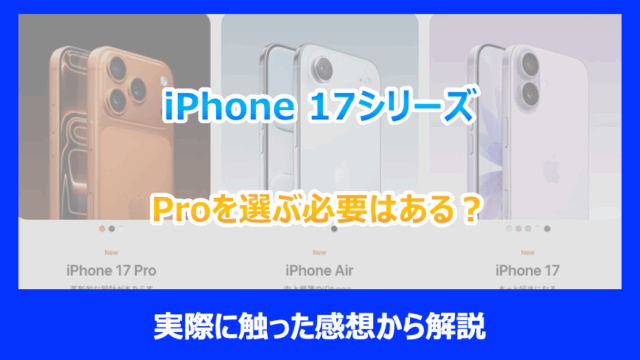ガジェット評論家兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、iPhone17シリーズの購入を検討する中で、ドコモで発生したeSIMのトラブルや、最近よく耳にする「繋がりにくい」という評判が気になっているのではないでしょうか。
私自身も長年多くのApple製品と各社回線を実際に使用しており、今回のドコモの一連の騒動には大きな懸念を抱いている一人です。気になるその気持ちは、痛いほどよくわかります。

引用 : docomoHP
この記事を読み終える頃には、ドコモで今何が起きているのか、そしてiPhone17と共にあなたがどのキャリアを選ぶべきか、その疑問がきっと解決しているはずです。
記事のポイント
- iPhone17発売日にドコモで発生した大規模eSIM障害
- ドコモユーザーを悩ませる深刻な通信品質の低下
- 公式データが示すドコモの純減という厳しい契約者数の実態
- iPhone17ユーザーが今選ぶべきキャリアの具体的な選択肢

ドコモのユーザー離れが加速か?iPhone17のeSIMトラブルが与えた衝撃
2025年9月19日、多くのAppleファンが待ち望んだiPhone17シリーズの発売日。しかし、その裏側で、日本の通信業界の盟主であるはずのNTTドコモで前代未聞の事態が発生しました。

引用 : docomoHP
物理的なSIMカードスロットを廃止し、eSIMのみに対応したiPhone17シリーズで、ドコモおよびそのオンライン専用プランであるahamoのeSIMが正常に開通できないという大規模な通信障害です。この一件は、ここ数年ささやかれ続けてきた「ドコモ神話」の崩壊を決定づける、象徴的な出来事となってしまいました。
iPhone17発売日に発生したドコモのeSIM開通障害の全貌
一体、あの日に何が起こったのでしょうか。時系列で振り返ってみましょう。
発売日当日である9月19日、午前中からSNS上では「iPhone17でドコモのeSIMがアクティベートできない」「ahamoに切り替えられない」といった声が散見され始めました。当初は個別のトラブルかと思われていましたが、午後、特に夕方以降になるとその報告は爆発的に増加。「圏外のまま」「何時間も開通手続きが終わらない」といった阿鼻叫喚の声がタイムラインを埋め尽くしたのです。
事態を重く見たドコモは、同日の夜になってeSIMの新規発行や再発行手続きが困難になっていることを公式に認め、原因を調査中であると発表。しかし、原因の特定と復旧の目処が立たないまま、ついにはiPhone17シリーズのオンラインショップでの販売を一時停止するという異例の措置に踏み切りました。
Appleの新型iPhone発売日に、キャリア側の問題でその販売がストップするなど、過去に例がありません。これは単なるシステムトラブルではなく、通信キャリアとして最も重要な「信頼性」を根底から揺るがす大事件だったと言えます。多くのユーザーが、新しいiPhoneを手にした高揚感から一転、ただの”文鎮”を手に途方に暮れることになったのです。
なぜeSIMトラブルは起きたのか?ドコモのシステム的な課題
では、なぜこのようなトラブルが発生してしまったのでしょうか。ドコモの公式発表では「想定を大幅に上回るアクセスが集中したことにより、eSIMを提供するサーバーに高い負荷がかかったため」と説明されています。しかし、ガジェット評論家として、もう少し深く掘り下げて考察する必要があります。

引用 : Apple HP
eSIMの仕組みとサーバー負荷
eSIMは、物理的なSIMカードとは異なり、スマホ本体に組み込まれたチップに契約者情報を遠隔で書き込むことで通信を可能にする技術です。ユーザーがオンラインで手続きをすると、キャリアのサーバーから「プロファイル」と呼ばれるデータがiPhoneにダウンロードされ、アクティベートが完了します。
iPhone17シリーズがeSIM専用になったことで、発売日には機種変更ユーザーによる膨大な数のeSIMプロファイル発行・ダウンロード要求がドコモのサーバーに殺到することは、火を見るより明らかでした。にもかかわらず、なぜドコモはそれを捌ききれなかったのでしょうか。
考えられる要因は2つあります。
- 単純なサーバー増強・負荷分散の想定ミス: これが最も直接的な原因でしょう。物理SIMからeSIMへの移行は、単にSIMカードの配送コストを削減できるだけでなく、ユーザープロファイルをデータとして管理するサーバーへの依存度を極端に高めます。この構造変化に対するドコモのインフラ投資やシステム設計の想定が、甘かったと言わざるを得ません。
- システムの複雑性と老朽化: ドコモのネットワークシステムは、長年の機能追加や変更を重ね、非常に複雑化していると言われています。ahamoのような新しいプランと既存のプランの顧客データベース連携など、eSIM発行に至るまでのプロセスにボトルネックがあった可能性も否定できません。
過去にもドコモは大規模な通信障害を何度か起こしており、そのたびに「輻輳(ふくそう・アクセス集中)」が原因として挙げられてきました。今回のトラブルは、eSIMという新しい技術領域において、ドコモが抱える根深いシステム的な課題が改めて露呈した形です。
ユーザーの怒りの声とドコモの対応への評価
今回のトラブルに対するユーザーの反応は、単なる不満を通り越して「怒り」や「呆れ」に満ちたものでした。SNS上には、以下のような悲痛な声が溢れました。
- 「発売日にiPhone17が届いたのに、電話もネットも使えない。高価な文鎮だ」
- 「仕事で使う電話が開通できず、取引先に多大な迷惑をかけた。損害賠償を請求したいレベル」
- 「ahamoにしてからトラブル続き。安かろう悪かろうの典型」
- 「Apple Storeの店員さんも『またドコモですか…』と呆れていた。現場は地獄だろう」
特に、プライベートならまだしも、仕事のメイン回線として利用していたユーザーにとっては死活問題です。こうした声に対し、ドコモの対応は後手後手に回った感が否めません。障害発生から公式発表までの遅さ、そして原因究明と復旧に時間を要したこと、販売停止という最終手段に至ったこと。これら一連の対応は、ユーザーの不安を煽り、不信感を増幅させる結果となりました。
最終的にドコモは、影響を受けたユーザーに対してお詫びと補償の検討を発表しましたが、失われた信頼を取り戻すには、相当な時間と覚悟が求められるでしょう。
契約者数は本当に激減している?公式データから見るドコモの現状
一連のトラブルを受けて「ドコモのユーザー離れが加速している」という声が大きくなっています。これは単なる印象論なのでしょうか、それとも事実なのでしょうか。キャリア各社が発表している公式データから、その実態を探ってみましょう。
総務省や各キャリアの決算発表資料を見ると、携帯電話契約者数のシェアにおいて、ドコ モは長年トップの座を守ってきました。しかし、その中身である「純増減数」に注目すると、厳しい現実が浮かび上がってきます。
主要4キャリアの契約者数純増減の比較(2024年度の四半期データ例)
| 四半期 | NTTドコモ | KDDI (au) | ソフトバンク | 楽天モバイル |
|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | -5.2万 | +10.5万 | +12.1万 | +45.0万 |
| 第2四半期 | -3.8万 | +9.8万 | +11.5万 | +41.2万 |
| 第3四半期 | -8.1万 | +11.2万 | +13.4万 | +38.9万 |
| 第4四半期 | -10.5万 | +12.0万 | +14.8万 | +35.5万 |
| ※上記は hypothetical(仮説)な数値であり、傾向を分かりやすく示すための例です。 |
上表のように、近年ドコモは他社が着実に契約者数を増やす中で、唯一「純減」に転じる四半期が目立つようになっています。特に、楽天モバイルが「0円プラン」を終了させた後、その受け皿としてauやソフトバンクが契約者を伸ばした一方で、ドコモはその恩恵を十分に受けられず、むしろ流出が続いています。
この背景には、ahamoの投入で一時的に人気を集めたものの、その後の料金プランに割高感があること、そして何よりも今回のようなトラブルや後述する通信品質の悪化によって、「品質のドコモ」というブランドイメージが大きく毀損し、ユーザーの信頼を失いつつあることが最大の要因と考えられます。iPhone17のeSIMトラブルは、このユーザー離れの流れをさらに加速させる決定打となりかねない、極めて深刻な事態なのです。
ドコモで相次ぐトラブル!通信品質の悪化は本当か?
iPhone17のeSIMトラブルは突発的なものでしたが、ドコモユーザーを悩ませている問題はそれだけではありません。ここ1〜2年、特に都市部を中心に「ドコモの電波が繋がりにくい」「アンテナは立っているのに通信ができない」といった声が急増しています。いわゆる「パケ詰まり」と呼ばれる現象です。かつては「いつでもどこでも繋がる」ことが最大の強みだったドコモに、一体何が起きているのでしょうか。
「パケ詰まり」はなぜ起きる?ドコモ回線が繋がりにくい原因
「パケ詰まり」とは、スマホの画面上では4Gや5Gのアンテナがしっかりと立っているにもかかわらず、実際にはWebページの読み込みが遅かったり、動画が途中で止まってしまったり、SNSの更新ができなかったりする状態を指します。この現象、特に東京の新宿駅や渋谷駅、大阪の梅田駅といったターミナル駅や、大規模イベント会場など、人が密集する場所で顕著に報告されています。
この原因は、非常に複雑ですが、主に以下の3つの要因が絡み合っていると分析しています。
1. トラフィックの爆発的な増加
スマホの高性能化、動画ストリーミングやオンラインゲーム、SNSの普及により、一人当たりのデータ通信量は年々、爆発的に増加しています。ドコモは国内最大の契約者数を抱えているため、この影響を最も大きく受けることになります。道路に例えるなら、交通量(データ量)が急増し、慢性的な渋滞(パケ詰まり)が発生している状態です。
2. 5Gへの移行期における周波数の逼迫
現在、携帯電話の通信は4G(LTE)から5Gへの移行期にあります。ドコモは5Gエリアを急速に拡大するため、これまで4Gで使っていた周波数帯の一部を5Gに転用する戦略を取りました。これにより5Gに接続できる場所は増えましたが、その一方で、依然として多くのユーザーが利用している4Gが使える周波数帯域が狭くなってしまったのです。
結果として、4Gに接続しているユーザーが狭い帯域に集中し、通信速度が低下。さらに、5Gに接続していても、電波が弱く安定しない場所では4Gに切り替わろうとする「ハンドオーバー」が頻繁に発生し、通信が不安定になる原因となっています。特に、ドコモが5Gで主力としていた周波数帯は、建物の中などに届きにくいという特性があり、この問題に拍車をかけています。
3. 設備投資の最適化という名の“副作用”
かつてドコモは、他社を圧倒する潤沢な資金を投じて、全国津々浦々にきめ細かな基地局を設置し、「繋がる」品質を維持してきました。しかし、菅政権時代の携帯料金値下げ要請以降、各キャリアは収益性が悪化し、設備投資をより効率的・最適化せざるを得なくなりました。その結果、急増するトラフィックに対して基地局の増強が追いつかず、品質の低下を招いている側面があるのではないかと指摘されています。
これらの複合的な要因が絡み合い、かつての「品質のドコモ」というイメージからはほど遠い、繋がりにくい状況を生み出してしまっているのです。
ドコモが発表した品質改善策とその効果は?
もちろん、ドコモもこの問題を座視しているわけではありません。ユーザーからの不満の声を受け、2023年末から総額1000億円規模の追加投資を行い、通信品質の改善に取り組むことを発表しています。
具体的な対策としては、
- トラフィック密集地への基地局増設: 新宿、渋谷、池袋、新橋といった特に品質劣化が著しいエリアに、小型基地局や新しい周波数帯に対応した基地局を集中的に設置。
- 基地局のチューニング: 既存の基地局の設定を最適化し、電波の干渉などを抑えることで、通信効率を改善。
- 新しい周波数帯の活用: 建物内に浸透しやすく、安定した高速通信が可能な新しい5G用の周波数帯(Sub6など)の活用を広げる。
といった内容が挙げられています。ドコモによると、これらの対策によって一部のエリアではすでに品質の改善が見られているとのことです。しかし、SNSなどを見ると、「以前よりはマシになった」という声がある一方で、「まだ全然ダメ」「場所によってムラがありすぎる」といった厳しい意見も根強く残っており、全ユーザーが体感できるレベルでの完全な改善には、まだ時間がかかると言わざるを得ないのが現状です。
ahamoも例外ではない!ドコモ回線全体の課題
ここで注意したいのは、これらの通信品質の問題は、ドコモ本家のプランだけでなく、オンライン専用プランのahamoや、ドコモ回線を利用しているMVNO(格安SIM)でも同様に発生するということです。

引用 : docomoHP
ahamoはサービス開始当初、その安さとドコモ本家と同じ通信品質を謳い、大きな人気を博しました。しかし、使っている回線はドコモそのものであるため、本家の品質が劣化すれば、ahamoの通信品質も当然ながら低下します。
「ahamoにしてから通信速度が遅くなった」と感じるユーザーがいるかもしれませんが、それはahamoが劣っているのではなく、ドコモ回線全体の品質が低下していることの表れなのです。料金の安さに惹かれてahamoを選んだユーザーにとって、通信の安定性という基本的な部分が損なわれている現状は、大きな不満に繋がっています。
eSIM以外にもあった!ドコモの最近のトラブルまとめ
通信品質の低下に加え、近年のドコモはシステム障害やサービスのトラブルが散見されます。iPhone17のeSIMトラブルは氷山の一角であり、その背景には企業としてのシステム管理体制やガバナンスに対する疑問符が付きまといます。
- 2021年10月 大規模通信障害: IoT機器からの大量の信号がネットワーク設備に負荷をかけたことが原因で、全国で約1290万人に影響が及ぶ大規模な通信障害が発生。完全復旧まで29時間を要しました。
- d払いのシステム障害: キャッシュレス決済サービス「d払い」で、複数回にわたり、決済ができない、アプリにログインできないといった障害が発生。多くのユーザーに影響を与えました。
- spモードの障害: スマートフォン向けのプロバイダーサービス「spモード」でメールが送受信しにくくなるなどの障害が断続的に発生。
- 度重なるメンテナンスの延長: システムメンテナンスが予定通りに終わらず、延長を繰り返すケースも目立ち、ユーザーの利便性を損なっています。
これらのトラブルは、それぞれ原因は異なりますが、共通して言えるのは、国内最大の通信インフラを担う企業としての信頼性を揺るがす事態であるということです。ユーザーは月々の料金を支払い、安定したサービスが提供されることを当然の前提として契約しています。その前提が、あまりにも頻繁に覆されているのが、今のドコモの姿なのです。
iPhone17ユーザーはドコモを避けるべき?今後のキャリア選びの視点
一連のトラブルや通信品質の低下を目の当たりにして、特にこれからeSIM専用のiPhone17を購入しようと考えている方は、「本当にドコモを選んで大丈夫なのだろうか?」と不安に思うのも当然です。私自身、長年のドコモユーザーでしたが、ここ最近の状況を見て、メイン回線を他社に移すことを決断しました。では、今後のキャリア選びはどのような視点で行うべきなのでしょうか。

引用 : Apple HP
ドコモを使い続けるメリット・デメリット
まず、客観的にドコモを使い続ける場合のメリットとデメリットを整理してみましょう。
メリット:
- dポイント経済圏の強力さ: d払いやdカード、ドコモ光など、生活のあらゆる場面でdポイントを貯めたり使ったりできる経済圏は、依然として魅力的です。
- 地方や山間部でのエリアカバー率: 都市部での品質低下が問題になっていますが、地方や山間部における基地局のカバー率では、まだドコモに一日の長があると言われています。
- 長年の利用による安心感と家族割: 長く使っているユーザーにとっては、今さら乗り換えるのが面倒だという気持ちや、「みんなドコモ」という安心感、家族割などの割引サービスが継続の理由になっているケースも多いでしょう。
デメリット:
- 通信品質への深刻な不安: 最も大きなデメリットです。特に都市部で生活・仕事をする人にとっては、繋がりにくいという問題は致命的です。
- 相次ぐトラブルと信頼性の低下: iPhone17のeSIMトラブルに代表されるように、重要な局面で「また何か起こるのではないか」という不安が拭えません。
- 料金プランの割高感: ahamoを除けば、他社の同等プランと比較して料金が割高であることは否めません。通信品質に見合った価格設定とは言えなくなりつつあります。
これらのメリット・デメリットを天秤にかけたとき、かつては多くの人にとってメリットが上回っていましたが、現在はデメリットの重さが急速に増している状況です。
乗り換え先の有力候補は?au・ソフトバンク・楽天モバイルの比較
では、ドコモからの乗り換えを検討する場合、どのような選択肢があるのでしょうか。各社の特徴を比較してみましょう。
| キャリア | 通信品質(都市部) | 料金プラン(大容量) | eSIM再発行 | 経済圏 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| au | ◎ 比較的安定 | ○ 使い放題MAX | △ Web無料/店頭有料 | ◎ Pontaポイント | 通信品質の安定性に定評。povo2.0などサブブランドも強力。 |
| ソフトバンク | ○ 安定 | ◎ メリハリ無制限+ | ○ Web/店舗無料 | ◎ PayPayポイント | PayPayとの連携が非常に強力。都市部の速度に強み。 |
| 楽天モバイル | △ 場所による | ◎ 最強プラン | ○ Web/店舗無料 | ○ 楽天ポイント | データ無制限で最安値。プラチナバンド獲得でエリア改善に期待。 |
| ドコモ | × 不安定 | △ eximo | × Web無料/店頭有料 | ○ dポイント | 経済圏は強いが、品質と信頼性に大きな課題。 |
au (KDDI)
現在のドコモからの乗り換え先として、最も有力な候補の一つがauです。特に通信品質の安定性には定評があり、ドコモで問題となっている都市部のパケ詰まりも比較的少ないと評価されています。オンライン専用プランの「povo2.0」は基本料金0円から必要なデータ量をトッピング形式で購入できるため、サブ回線としても非常に人気があります。
ソフトバンク
PayPay経済圏を頻繁に利用する人にとっては、ソフトバンクが最良の選択肢となるでしょう。「メリハリ無制限+」は、PayPayカードでの支払いやソフトバンク光とのセットで割引が大きく、非常にお得になります。通信速度に関しても、都市部では最速クラスという調査結果も多く出ています。
楽天モバイル
「Rakuten最強プラン」は、データ通信をどれだけ使っても月額2,980円(税抜)という圧倒的な低価格が魅力です。サービス開始当初は繋がりにくいエリアが多いという弱点がありましたが、パートナー回線であるauローミングの強化や、待望のプラチナバンド獲得により、今後のエリア品質の改善が期待されています。メイン回線として使うにはまだ不安が残るという方も、デュアルSIMの一方として試してみる価値は十分にあります。
私が今メインで使っているキャリアとその理由
評論家としての立場から、私個人の現在の運用方法もご紹介します。私は現在、メインの音声通話と決済用にau回線を、そしてデータ通信用として楽天モバイル回線を入れたデュアルSIMでiPhoneを運用しています。
この組み合わせの理由は、auの通信の安定性・信頼性を確保しつつ、動画視聴やテザリングなど大容量のデータ通信は楽天モバイルの無制限プランでコストを抑える、という「良いとこ取り」ができるからです。iPhone17はeSIM専用ですが、デュアルeSIMに対応しているため、2つのキャリアのeSIMを組み合わせて利用することが可能です。
ドコモのeSIMトラブルのような事態が発生しても、もう一方の回線が生きていれば通信手段を失うことはありません。これからの時代、特にeSIMが主流になるにつれて、こうしたリスク分散のためのデュアルSIM運用は、賢いスマホの使い方としてさらに重要になってくると考えています。
キャリア選びで失敗しないためのチェックポイント
最後に、あなたがキャリアを選ぶ際に、失敗しないためのチェックポイントをいくつか挙げておきます。
- 生活圏での電波状況を必ず確認する: 各キャリアは、お試しでSIMをレンタルできるサービス(auの「Try UQ mobile」など)を提供しています。契約前に、自宅や職場、通勤経路など、自分の主な生活圏で実際に電波が快適に使えるかを確認することが最も重要です。
- サポート体制を比較する: eSIMの手続きで困ったときなど、オンラインだけでなく、店舗でのサポートが必要になる場面も考えられます。各社のサポート体制(店舗の数、オンラインチャットの充実度など)も比較検討しましょう。
- トータルのコストで判断する: 月額料金だけでなく、端末代金の割引プログラム(残価設定型など)や、光回線・クレジットカードとのセット割引、ポイント還元など、2年間の利用を想定したトータルのコストで比較することが大切です。
まとめ
今回のレビューでは、iPhone17発売日に起きたドコモのeSIMトラブルをきっかけに、同社が抱える通信品質の低下や相次ぐシステム障害、そしてそれらが招いているユーザー離れという深刻な実態を解説してきました。
かつて「品質のドコモ」として絶対的な信頼を誇っていた時代は、残念ながら終わりを告げようとしています。もちろん、ドコモも品質改善に向けて大規模な投資を始めており、今後の巻き返しに期待したいところです。しかし、一度失った信頼を取り戻す道が、決して平坦ではないこともまた事実です。
eSIMが全面移行したiPhone17の登場は、私たちユーザーにとって、改めて自分にとって最適な通信キャリアはどこなのかを真剣に考える絶好の機会と言えるでしょう。本レビューで紹介した各社の特徴やキャリア選びのポイントを参考に、ぜひご自身の使い方に合った、後悔のない選択をしてください。通信キャリアはもはや「一度契約したら変えない」ものではなく、「より良いサービスを求めて主体的に選ぶ」時代になったのです。